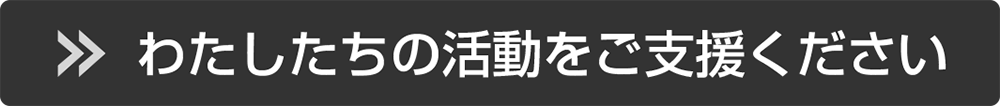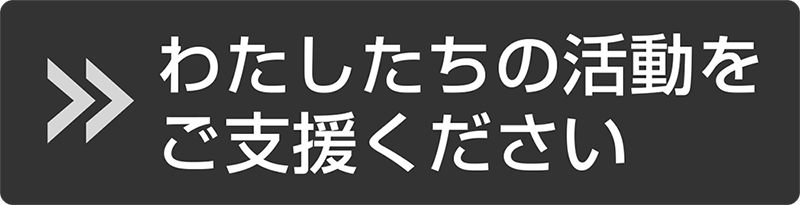引きこもり支援
スポーツと文化の力で、子どもたちに社会への一歩を
引きこもりの現状
内閣府調査(2023年3月公表)によると、15~39歳まで推計で約49万人(全体では146万人と推計)が引きこもり状態にあります。引きこもりの入り口となりやすいのが不登校です。文部科学省調査(2022年度)によると、小中学校の不登校は約29万9千人で過去最多となっています。不登校が長期化すると、引きこもり状態に移行するケースがあるため、不登校のこどもたちもケアする必要があります。
※「引きこもり」の定義は、「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態」(厚生労働省・内閣府)とされています。ただし、広義の定義として、趣味の用事や近所の買い物などには外出している人も含まれる場合があります。
引きこもりの問題点・心配される点
こども本人起こる問題・心配される点
家族以外との交流機会の極端な減少により、社会生活を営むためのコミュニケーション能力や対人関係スキルが低下し、社会復帰のハードルが上がります。うつ病、不安障害などの精神疾患を併発するリスクも高まります。また、昼夜逆転、運動不足による身体疾患のリスクも高まり、心身の健康が損なわれます。社会(学校生活)から切り離された状態が続くことで、「自分はダメだ」という自己否定感が強くなり、支援への抵抗感や諦めにつながります。
家族に起こる問題・心配される点
周囲に相談できず、家族だけで問題を抱え込み、孤立するケースが多く、特に母親への心理的・身体的負担が大きくなり、家族のメンタルヘルスも損なわれます。そのまま引きこもりが長期化して、こどもが大人になっても生活を支える状況になると、親の高齢化・病気・介護によって生活の維持が困難になり、共倒れのリスクが極めて高くなります。家庭内で暴力が発生し、家族が身の危険を感じながら生活しているケースもあります。。引きこもり支援プログラム






対人関係のトレーニングと居場所作り
プロ選手や民間教室の専門家、他の参加者との関わりを通じて、社会参加の第一歩となる「安心できる居場所」と「他者との関わり」を提供します。自己肯定感の回復
スポーツや文化活動を通じて「できた!」という成功体験を積み重ね、自己肯定感を回復させる機会をつくります。社会との接点
スリランカの孤児院をサポートする海外支援です。18歳で卒院した身寄りのないこどもたちを日本の大学に留学させて人生を応援するプロジェクトです。開催スケジュール
| サッカー | 準備中です。 |
|---|---|
| 野球 | 準備中です。 |
| 書道 | 準備中です。 |
| バスケット | 準備中です。 |
| ダンス | 準備中です。 |
| 総合格闘技 | 準備中です。 |
目指す未来
徹底した自己省察と内省力
外部からの刺激や社会の価値観に左右されず、自分自身の感情、興味、価値観、苦手なことと徹底的に向き合う時間を持つことで、深い自己理解が得られます。この内省力は、仕事や人間関係で壁にぶつかった際に、自分を見失わず、冷静に状況を分析し、乗り越えるための原動力となります。特定分野への深い探求と専門知識
外部との接触が少ない環境で、趣味や興味の対象(読書、プログラミング、芸術、ゲームなど)に没頭することで、高い集中力や専門的な知識・スキルを身につけることがあります。 特にインターネットを通じて学んだスキル(Webデザイン、翻訳、特定のデータ分析など)は、社会復帰後のユニークな才能として評価され、ニッチな分野で役立つ可能性があります。他者の苦しみへの共感性・受容力
社会生活の難しさを経験した当事者として、生きづらさを抱える他者や、マイノリティの立場にある人々の苦しみに対し、深く共感し、受容する能力が育まれます。 この共感性の高さは、福祉、教育、カウンセリングなど、他者を支援する仕事で大きな強みとなり得ます。既存の価値観にとらわれない柔軟な視点
「みんなと同じようにしなければならない」という画一的な社会の価値観から一時的に距離を置いたことで、既存の常識や社会システムに対して、批判的かつ多角的な視点を持つことができます。独自の生き方の構築: 組織に属する以外の働き方や、多様な生き方を受け入れる柔軟性が高まり、自分らしい人生を再構築する力になります。森と木訪問看護ステーション

精神疾患をお持ちの方、不安で眠れない方、誰かに話を聞いてほしい方、精神科経験があるスタッフが親身になって、利用者様だけでなくご家族にも寄り添う、訪問看護ステーションです。住み慣れたご自宅で、一人ひとりのライフスタイルに合わせて「自分らしく生きるとは何か」を一緒に考え、「やってみたい思いを実現させる」サポートを行い、社会復帰していける道を共に目指します。
引きこもり家族会
ひきこもり支援の第一人者である山根俊恵先生のSDS支援支援者養成講座の研修を受けて、山梨モデルを確立させていくべく家族会を実施し、引きこもり支援をしています。家族心理教育を行い、ひきこもりのメカニズムやご本人の生きづらさ、家族が本人とどう向き合い、声をかけたら良いのか、何か先回りなのかなど具体的に学び合い、親が変わっていくサポートを行います。そうすると、「ドアが開いた」「返事をした」「生活音がするようになった」「暴言・暴力がなくなった」「何が苦しいか言えるようになった」「家では普通になった」「病院に行くようになった」などの変化を起こしてきます。家族が笑顔を取り戻すことは、本人にとっても大きな希望

精神科訪問看護師として、在宅療養中の方の心身のケアや服薬管理、生活リズムの調整などを行い、利用者と家族双方に寄り添った支援を実践。不登校や家庭内孤立などの課題を抱える子どもたちや保護者に対して、家庭・学校・地域・行政と連携しながら、安心して過ごせる環境づくりを支援してきました。
引きこもりのこどもたちを支援するにあたり、山根先生のモデルを選んだのは、「本人をどう動かすか」よりも、「家族がどう安心を取り戻し、どう本人に寄り添えるか」という部分を何よりも大切にしているからです。支援の軸が「本人」だけでなく「家族」「地域」に広がっている点が、現場の訪問支援の考え方と非常に近く、実践につながるものでした。
また、山根先生のモデルでは、支援者が“専門家として指導する”のではなく、共に悩み、共に考える伴走者として関わる姿勢が根底にあります。
その考え方に触れ、「支援」とは「変えようとすること」ではなく、「理解し、共に歩むこと」なのだと改めて感じました。だからこそ私は、この山根モデルを実践の軸に据え、SDS支援者養成講座を受講し、地域の中で引きこもり支援として家族会を立ち上げようと思いました。一人でも多くのご家族が、孤立せずに語り合える場所をつくることが、私の支援の出発点となっています。
これからの支援で大切にしていきたいのは、「安心してつながれる居場所を増やしていくこと」です。引きこもりや生きづらさを抱える子どもや家族は、助けを求めること自体に大きな不安や抵抗を感じていることが多くあります。だからこそまず「話してもいい」「相談してもいい」と思えるような、小さな一歩を支える場をつくっていきたいと考えています。
そのために、医療・福祉・教育・地域がそれぞれの立場で関わりながら、お互いの強みを生かして支え合えるような連携を進めていきたいと思っています。地域全体で“見守る力”を育てていくことが、今後の支援の鍵になると感じています。
また、本人だけでなく、家族が安心して自分の気持ちを話せる場づくりにも力を入れていきたいです。家族が笑顔を取り戻すことは、本人にとっても大きな希望になります。引きこもりの子どもたちが「社会とつながる」ことをゴールにするのではなく、“自分らしく生きられる場所”を見つけられることを目指していきたいと思います。
「子どもたちが安心して笑える社会は、大人が支え合える社会の中で育まれると思います。一人ひとりの『困りごと』の背景には、その人の人生や家族の物語があります。その思いに寄り添い、誰もが“自分らしく生きること”をあきらめない地域づくりを、これからも仲間と共に進めていきたいです。
森と木訪問看護ステーション マネージャー 山本侑里